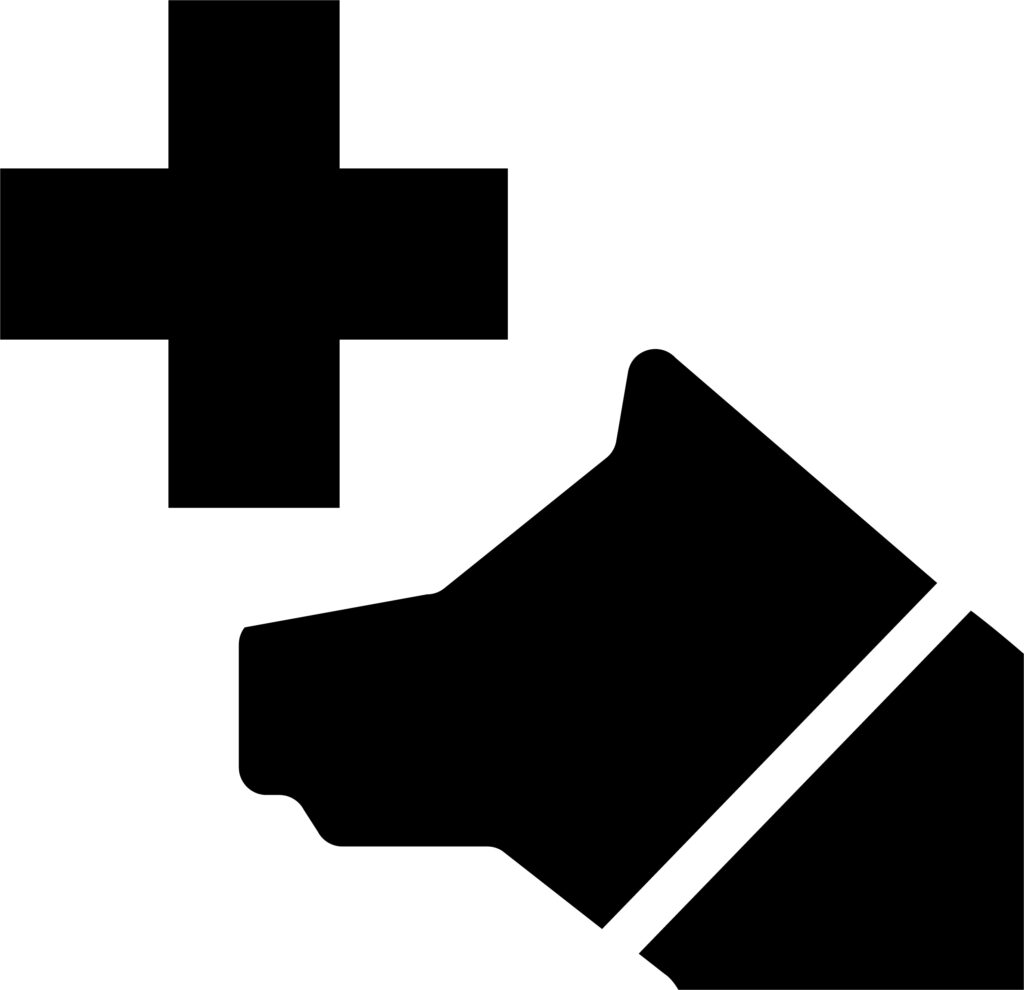ワクチン接種ガイド:犬と猫の種類・スケジュール・費用・副反応
目次
ワクチン接種ガイド:犬と猫の種類・スケジュール・費用・副反応
はじめに
「予防医療」の中でも、感染症から愛犬・愛猫を守るために非常に重要なのがワクチン接種です。ワクチンは、恐ろしい病気に対する抵抗力(免疫)を体につけさせ、感染を防いだり、もし感染しても症状を軽くしたりする効果があります。
このガイドでは、犬と猫のワクチンの種類、一般的な接種スケジュール、費用の考え方、そして副反応について詳しく解説します。甲賀地域にお住まいの皆様が、愛犬・愛猫に最適なワクチン計画を立てるための参考にしてください。
なぜワクチン接種が大切なの?
ワクチンは、病原体(ウイルスや細菌)の毒性を弱めたり、なくしたりしたものを体に入れることで、「この病原体は敵だ!」と体に覚えさせ、実際に本物の病原体が入ってきたときに戦えるように準備させる仕組みです。
ワクチン接種には、主に以下のような大切な理由があります。
- 命に関わる病気の予防: ジステンパーやパルボウイルス感染症(犬)、猫汎白血球減少症(猫)など、ワクチンで予防できる病気の中には、特に子犬・子猫で致死率が非常に高いものが含まれます [5]。
- 重症化の防止: たとえ感染しても、ワクチンを接種していれば症状が軽くて済む場合が多くなります。
- 感染拡大の防止: 多くのペットがワクチンを接種することで、地域全体での病気の流行を防ぐ「集団免疫」の効果も期待できます。
- 安心して暮らすために: ワクチンで予防することで、ドッグランやペットホテル、トリミングサロンなどを安心して利用できるようになります。
ワクチンの種類
ワクチンには、すべての犬・猫に接種が推奨される「コアワクチン」と、生活環境や地域のリスクに応じて接種を検討する「ノンコアワクチン」があります。
コアワクチン:すべての犬・猫に推奨
コアワクチンは、感染すると重篤な症状を引き起こし、広く流行している可能性のある病気を予防するもので、飼育環境に関わらず全ての犬・猫に接種が強く推奨されます。
| 動物種 | コアワクチンで予防できる主な病気 | 備考 |
| 犬 | ジステンパー、パルボウイルス感染症、アデノウイルス2型感染症(伝伝染性肝炎含む)、(パラインフルエンザ) | これらを組み合わせた混合ワクチン(例:5種混合 [6])が一般的 |
| 猫 | 猫ウイルス性鼻気管炎(FVR)、猫カリシウイルス感染症(C)、猫汎白血球減少症(P) | これらを組み合わせた3種混合ワクチン(FVRCP [7])が基本 |
※狂犬病ワクチン(犬のみ): 日本では、生後91日以上の犬への狂犬病ワクチンの接種と登録が法律で義務付けられています。これはコアワクチンとは別に、毎年1回の接種が必要です。
ノンコアワクチン:ライフスタイルやリスクに応じて選択
ノンコアワクチンは、生活環境(室内飼いか、屋外に出るか)、同居動物の有無、地域での病気の流行状況などを考慮し、獣医師と相談の上で接種を検討するワクチンです。
【犬の主なノンコアワクチン】
- レプトスピラ感染症:
- どんな病気?
- レプトスピラというらせん状の細菌によって引き起こされる感染症です。この菌は、感染したネズミなどの野生動物の腎臓に潜んでおり、尿とともに排出されます。その尿で汚染された水(水たまり、川、湖など)や土壌が感染源となります [3]。
- ワンちゃんは、汚染された水を飲んだり、地面の匂いを嗅いだり、水遊びをしたり、あるいは皮膚の小さな傷から菌が侵入することで感染します。
- **人にも感染する「人獣共通感染症」**であり [3]、人が感染するとインフルエンザ様の症状から、重症化すると黄疸、腎不全、出血などを起こすことがあります(ワイル病など)。ペットが感染源の菌を尿中に排泄したり、汚染された環境から人が直接感染したりするリスクがあるため、ワンちゃんの予防はご家族全員の健康を守る上でも重要です。
- 症状は?
- 感染した犬では、発熱、震え、元気消失、食欲不振、嘔吐、筋肉痛(触られるのを嫌がる)、脱水などの初期症状が見られることがあります。進行すると、肝臓や腎臓がダメージを受け、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、急性腎不全(急に水をたくさん飲む、尿が大量に出るまたは全く出なくなる)といった重篤な状態に陥り、命を落とすケースも少なくありません [4]。たとえ回復しても、腎臓や肝臓に後遺症が残ることもあります。
- 甲賀地域でのリスクとワクチン
- 滋賀県内での犬の感染歴(抗体保有)も報告されており [2](※過去の調査ではイクテロヘモラジー、カニコーラ、ヘブドマディス、オータムナリス等の血清型が検出)、決して他人事ではありません。
- 田畑、山、川など自然環境が豊かな甲賀地域では、野生動物との接触機会や、汚染された水・土壌に触れるリスクは常に存在します。特に、アウトドア活動(キャンプ、ハイキング、川遊びなど)を共に楽しむ場合、農作業の手伝いをする場合、あるいは自宅周辺にネズミが出没するような環境では、感染リスクが高まります。
- レプトスピラには非常に多くの「血清型」と呼ばれる種類が存在し、問題となる型は地域や時代によっても変化します。感染した型に対する免疫しか得られないため、複数の血清型に対応できるワクチンの接種が重要です。
- 現在主流となっているL4ワクチン [8] は、世界的に広く分布し、重症化しやすいとされる4つの主要な血清型(イクテロヘモラジー、カニコーラ、グリッポチフォーサ、ポモナ)に対応しています。滋賀県内で過去に検出された型の一部(イクテロヘモラジー、カニコーラ)もカバーしており、国際的なガイドラインでもリスクのある犬への接種が推奨されています [4]。
- ワクチンは主に重症化を防ぐことを目的としています。感染や尿中への菌の排泄を100%防ぐわけではありませんが、ワクチン接種により発症のリスクや症状の重篤度を大幅に低減させることができます [4]。診断も特殊な検査が必要な場合があるため[4]、予防が非常に重要です。
- 予防のポイント
- リスクのあるワンちゃんには年1回のワクチン接種が推奨されます [4]。
- 汚染されていそうな水たまりや水辺に近づけない、ネズミの駆除など、環境整備も補助的な予防策となります。
- どんな病気?
- ボルデテラ感染症(ケンネルコフの一部):
- 咳を主症状とする呼吸器感染症(ケンネルコフ)の原因の一つです。
- ペットホテルやドッグラン、トリミングサロンなど、他の犬との接触が多い場合に接種が推奨されます。
- 犬コロナウイルス感染症:
- どんな病気?
- 犬コロナウイルス(CCoV)によって引き起こされる腸炎です。感染犬の糞便との接触(糞便で汚染されたものを舐めるなど)で感染が広がります [5]。
- 症状は?
- 主に子犬で、突然の嘔吐や下痢(水様~粘液状、時に血が混じることも)、食欲不振、元気消失などの消化器症状を示します [5]。
- なぜノンコア?
- 成犬では感染しても無症状なことが多く、子犬でも通常は軽症で、数日~1週間程度で自然に回復することがほとんどです [5]。
- そのため、世界の主要なワクチンガイドライン(WSAVA、AAHAなど)では、全ての子犬への一律の接種は推奨されていません [5]。
- ただし、非常に幼齢の子犬や、衛生状態の良くない環境、他のウイルス(特にパルボウイルス)との混合感染が起きた場合には、症状が重くなる可能性も指摘されています [5]。
- ワクチンについて
- ワクチンは存在し、他のワクチンと混合されていることが多いです(例:6種混合 [11]、10種混合 [12])。
- 接種の必要性は、子犬を迎える環境(ペットショップ、ブリーダー、シェルターなどでの流行状況)、多頭飼育環境、あるいは特定の施設(ケンネルなど)で接種が要求される場合などを考慮して、獣医師と相談の上で判断します。
- どんな病気?
【猫の主なノンコアワクチン】
- 猫白血病ウイルス感染症(FeLV):
- 感染猫との接触(唾液、ケンカの咬み傷など)で感染し、免疫不全やリンパ腫などを引き起こすウイルスです。
- 屋外に出る猫、新しく猫を迎える場合、同居猫に感染猫がいる場合に接種が推奨されます。
- 接種前には感染の有無を確認する検査が必要です。アジュバント(免疫増強剤)を含まない組換え型ワクチン [10] もあります。
- 猫免疫不全ウイルス感染症(FIV:猫エイズ):
- 主にケンカの咬み傷で感染し、免疫不全を引き起こすウイルスです。
- 屋外に出る猫、特にオス猫でケンカをする可能性がある場合に接種が検討されます。
- 接種前には感染の有無を確認する検査が必要です。初回は3回接種が必要なワクチン [9] があります。
- クラミジア感染症:
- 結膜炎や鼻炎などを引き起こす細菌感染症です。
- 多頭飼育環境(シェルターなど)や、過去に感染があった場合に接種が検討されます。
混合ワクチン
多くのワクチンは、複数の病原体に対する成分を一つにまとめた「混合ワクチン」として接種されます。これにより、注射の回数を減らすことができます。
- 犬: 5種混合(コア)[6]、6種混合(コア+コロナ)[11]、8種混合(コア+レプトスピラ2種+パラインフルエンザ)、9種混合(コア+レプトスピラ4種)、10種混合(コア+コロナ+レプトスピラ4種)[12] など、様々な組み合わせがあります。
- 猫: 3種混合(コア)[7]、4種混合(コア+FeLV)、5種混合(コア+FeLV+クラミジア [10])などが一般的です。
どの混合ワクチンが最適かは、その子のライフスタイルやリスクによって異なりますので、獣医師とよく相談しましょう。
接種スケジュール
ワクチンは、適切な時期に適切な回数を接種することで、確実な免疫をつけることができます。
子犬・子猫の初回接種プログラム
生まれたばかりの子犬・子猫は、母乳(初乳)から免疫(移行抗体)をもらっています。この移行抗体は病気から守ってくれる一方で、ワクチンの効果を妨げてしまうことがあります。移行抗体は徐々に減少していくため、適切な時期に複数回のワクチン接種を行い、免疫を確実に獲得させることが重要です [1]。
- 開始時期: 通常、生後6~9週齢頃から開始します。
- 接種間隔: 3~4週間隔で接種します。
- 最終接種: 移行抗体の影響がなくなる生後16週齢以降に最後の接種を行うことが推奨されます。
- FIVワクチン(猫): 初回プログラムとして2~3週間隔で3回の接種が必要です [9]。
具体的なスケジュールは、ワクチンの種類や個々の状況によって異なります。
成犬・成猫の追加接種
初回接種プログラムで獲得した免疫も、時間とともに低下していきます。そのため、定期的な追加接種で免疫を維持することが重要です。
- 頻度: 多くのワクチンで年に1回の追加接種が推奨されています。特にレプトスピラワクチン [4] や狂犬病ワクチン(法律で規定)は毎年接種が必要です。
- 抗体検査: ワクチンの種類によっては、抗体価(免疫の強さ)を測定し、接種の必要性を判断する方法もあります。ただし、抗体価だけでは判断できない場合や、検査費用がかかる点も考慮が必要です。
最適な追加接種のタイミングや方法については、獣医師と相談して決めましょう。
費用について
ワクチン接種にかかる費用は、以下の要因によって異なります。
- ワクチンの種類: 混合されている種類が多いほど、費用は高くなる傾向があります。
- 動物病院の料金設定: 診察料などが含まれるかなど、病院によって異なります。
病気の治療にかかる費用と比較すれば、ワクチン接種は非常に費用対効果の高い投資と言えます。
当院での接種費用は以下の通りです。(診察料別)
作成中
副反応と安全性
現在の動物用ワクチンは、適切な品質管理のもと製造されており、非常に安全性が高いものです。しかし、体にとっては異物であるため、免疫が作られる過程で体に軽微な反応が起こることがあります。また、ごくまれに体質に合わない場合もあります。
一般的な副反応(軽度・一過性)
これらは免疫を獲得する過程で起こる比較的軽度な反応で、通常は接種後数時間~1日程度で自然に治まります。過度に心配する必要はありませんが、注意して様子を見てあげてください。
- 元気・食欲の低下: 少しだるそうにする、食欲が普段より落ちる。
- 注射部位の反応: 腫れたり、痛がったりする(触ると嫌がる、びっこを引くなど)。
- 発熱: 少し熱っぽくなる。
- 消化器症状: 軽い嘔吐や下痢。
注意すべき副反応(まれですが、注意が必要)
以下のような症状は、アレルギー反応(アナフィラキシーショックを含む)の可能性があり、緊急の対応が必要な場合があります。接種後はしばらく様子を観察し、異変があればすぐに動物病院にご連絡ください。
- 顔面の腫れ: まぶたや口の周りが急に腫れる(ムーンフェイス)。
- 皮膚症状: 体中を痒がる、皮膚に赤みやじんましんが出る。
- 呼吸の変化: 呼吸が速くなる、苦しそうにする。
- 循環器症状: ぐったりして立てなくなる(虚脱)、歯茎などが白っぽくなる。
- 消化器症状: 繰り返す嘔吐や激しい下痢。
- 神経症状: ふるえ、けいれん。
これらの重篤な反応は、通常、接種後30分~1時間以内に起こることが多いですが、数時間後に現れることもあります。接種当日は、なるべく安静にし、飼い主様がそばで様子をよく観察できる時間に接種を受けることをお勧めします。
猫の注射部位肉腫について
猫では、不活化ワクチン(特にアジュバントを含むもの、例:FIVワクチン [9])の接種部位に、まれに悪性の腫瘍(線維肉腫など)が発生することが報告されています。発生頻度は非常に低い(1/1000~1/10000程度 [9])とされていますが、当院ではリスクを最小限にするため、ワクチンの種類選択や接種部位に配慮しています。接種後にしこりが長期間残る、大きくなるなどの変化が見られた場合は、早めにご相談ください。
ワクチン接種に関するよくあるご質問 (FAQ)
Q1: 混合ワクチンと狂犬病ワクチンは、どれくらい間隔をあければいいですか?
A1: 同時接種は避けるべきです。ワクチンの種類にもよりますが、添付文書上は最低1週間あけるよう記載されています [13, 各混合ワクチン添付文書]。より安全性を考慮し、一般的には2~4週間程度の間隔をあけることをお勧めしています。詳しくは獣医師にご相談ください。
Q2: ワクチン接種後、お散歩や運動はいつから大丈夫ですか?
A2: 接種当日は安静にするのが基本です。激しい運動は、副反応が出やすくなる可能性や、注射部位の痛みを増強させる可能性があるため、接種後2~3日は避けるようにしましょう [各ワクチン添付文書参照]。軽いお散歩程度であれば、体調に変化がなく、本人が元気なようであれば問題ないことが多いですが、念のため獣医師にご確認ください。
Q3: ワクチン接種後、シャンプーやトリミングはいつから大丈夫ですか?
A3: シャンプーやトリミングも、接種後2~3日は避けるのが無難です [各ワクチン添付文書参照]。注射部位を刺激したり、体力の消耗につながったりする可能性があるためです。特に注射部位に腫れや痛みがある場合は、それらが治まるまで待ちましょう。
Q4: 複数のワクチン(例:混合ワクチンとレプトスピラ単独ワクチン)を同じ日に打てますか?
A4: いいえ、原則として異なる種類のワクチンの同時接種は避けるべきです [各ワクチン添付文書参照]。それぞれのワクチンに対する適切な免疫応答を促し、副反応が出た場合の原因特定を容易にするためです。どのワクチンをどの順番で、どれくらいの間隔をあけて接種するかは、獣医師がその子の状況に合わせて計画します。
Q5: ワクチン接種と同じ日に、ノミ・ダニ予防薬(スポットオンやおやつタイプ)を使っても大丈夫ですか?
A5: 一般的に、動物病院で処方されるノミ・ダニ・フィラリアなどの予防薬(例:フロントラインプラス® [14]、ネクスガードスペクトラ® [15]、レボリューションプラス® [16]など)は、ワクチン接種と同日または近い時期に使用しても、それぞれの効果に影響はないと考えられています。これらの予防薬の添付文書には通常、ワクチンとの相互作用に関する特別な注意喚起はありません。ただし、念のため、接種当日の体調を考慮して、同時投与・投薬を避ける場合もあります。ご心配な場合や、具体的な投与タイミングについては、必ず獣医師にご相談ください。
Q6: ワクチンを接種すれば、その病気に絶対かからなくなりますか?
A6: ワクチンは病気に対する抵抗力(免疫)を非常に高めますが、残念ながら100%の発症予防を保証するものではありません。個体差やウイルスの変異などにより、まれに感染・発症する可能性(ブレイクスルー感染)はあります。しかし、ワクチンを接種していれば、たとえ発症しても症状が軽度で済むことがほとんどです。定期的な追加接種で免疫を維持することが重要です。
Q7: ワクチンの効果はどれくらい続きますか?毎年接種が必要ですか?
A7: ワクチンの種類や個体によって免疫の持続期間は異なります。コアワクチンの中には、成犬・成猫では3年以上免疫が持続するものがあるという報告もあり、近年では3年ごとの接種プロトコルが検討されることもあります。一方で、レプトスピラワクチン[4]や狂犬病ワクチン(法律で義務)のように、確実な予防効果を維持するために毎年接種が必要なものもあります。最適な接種間隔については、最新のガイドラインやペットの状況に基づき、獣医師と相談して決めることが大切です。
Q8: 抗体検査とは何ですか?受けた方がいいですか?
A8: 抗体検査は、特定の病気(主に犬のジステンパー、パルボウイルス、猫の汎白血球減少症など)に対する免疫(抗体価)が十分にあるかを血液で調べる検査です。抗体価が十分にあれば、その年のコアワクチンの追加接種を見送る判断材料の一つになることがあります。ただし、抗体価だけでは防御能を完全に証明できるわけではなく、検査ができないワクチン(レプトスピラなど)もあります。検査費用もかかるため、実施するかどうかはメリット・デメリットを獣医師とよく相談して決めましょう。
Q9: 高齢のペットや持病がある子でもワクチンは打てますか?
A9: 高齢であることや持病があることだけで、ワクチン接種が不可能になるわけではありません。ただし、健康状態によっては接種を見合わせたり、慎重な判断が必要になったりする場合があります。その子の健康状態、生活環境、感染リスクなどを総合的に評価し、接種するメリットがリスクを上回ると判断されれば接種を行います。必ず事前に獣医師に健康状態を伝え、相談してください。
Q10: ワクチン証明書はどんな時に必要になりますか?
A10: ワクチン接種証明書は、ペットホテル、トリミングサロン、ドッグランなどの施設利用時や、ペット同伴での旅行(特に海外渡航)、ドッグショーなどのイベント参加時に提示を求められることが一般的です。狂犬病ワクチンについては、自治体への登録や鑑札・注射済票の交付に必要です。大切な書類ですので、紛失しないように保管しましょう。再発行には手数料がかかります。
まとめ:最適なワクチンプログラムのために
ワクチン接種は、愛犬・愛猫を様々な感染症から守るための、最も効果的な予防策の一つです。しかし、どのワクチンをいつ接種するのが最適かは、その子の年齢、健康状態、ライフスタイル、そしてお住まいの地域(甲賀地域)のリスクによって異なります。
**ワクチンに関する考え方や推奨されるプロトコルは、新しい知見によって変化することもあります。**インターネットの情報だけを鵜呑みにせず、必ず獣医師にご相談ください。当院では、一頭一頭の状況を詳しくお伺いし、常に最新の情報を考慮しながら、その子にとって現時点で最善と考えられるワクチンプログラムをご提案いたします。
- 予防医療全般へ戻る → 【甲賀地域の皆様へ】犬猫の健康を守る「予防医療」のススメ
参考文献
- 竹内和義(監修). 子犬と子猫の診療ガイド. 緑書房.
- 河南明孝, 土井大輔 (2008). 滋賀県下の犬におけるレプトスピラ抗体保有状況. 日本獣医師会雑誌, 61(8), 645-647.
- 国立感染症研究所. レプトスピラ症とは. (参照年月日:YYYY-MM-DD) ※ウェブサイトの場合は参照日を記載
- Sykes JE, et al. (2023). Updated ACVIM consensus statement on leptospirosis in dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine. DOI: 10.1111/jvim.16903
- 石田卓夫(総監修) (2020). 犬の内科診療 Part 1. 緑書房.
- ゾエティス・ジャパン株式会社. バンガード® プラス 5 添付文書 (2025年1月改訂).
- ゾエティス・ジャパン株式会社. フェロセル® CVR 添付文書 (2025年1月改訂).
- ゾエティス・ジャパン株式会社. バンガード® L4 添付文書 (2025年1月改訂).
- ゾエティス・ジャパン株式会社. フェロバックス® FIV 添付文書 (2023年12月改訂).
- ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社. ピュアバックス® RCPCh-FeLV 0.5 添付文書 (2022年9月作成).
- ゾエティス・ジャパン株式会社. バンガード® プラス 5/CV 添付文書 (2024年11月改訂).
- ゾエティス・ジャパン株式会社. バンガード® プラス 5/CV-L4 添付文書 (2025年1月改訂).
- 日生研株式会社. 日生研狂犬病TCワクチン 添付文書 (2024年4月改訂).
- ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社. フロントライン® プラス ドッグ 添付文書 (2022年6月改訂).
- ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社. ネクスガード® スペクトラ 添付文書 (2024年11月改訂).
- ゾエティス・ジャパン株式会社. レボリューション® プラス 添付文書 (2021年10月改訂).