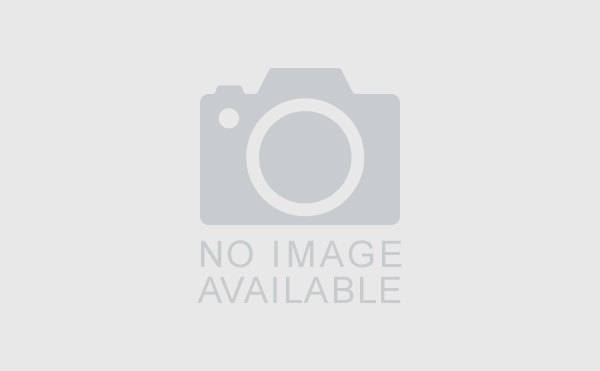お腹の虫(消化管内寄生虫)とその対策
目次
お腹の虫(消化管内寄生虫)とその対策【甲賀地域の犬と猫のために】
はじめに:見えないけれど身近な脅威
愛犬・愛猫のお腹の中に寄生する虫(消化管内寄生虫)は、目に見えないことが多いため、気づかないうちに感染しているケースも少なくありません。特に子犬や子猫では、母犬・母猫から感染している可能性が高いと言われています。
これらの寄生虫は、下痢や嘔吐、栄養不良といったペット自身の健康問題を引き起こすだけでなく、中には**人に感染して健康被害を及ぼすもの(人獣共通感染症)**も存在します。
このページでは、犬や猫でよく見られる消化管内寄生虫の種類、感染経路、症状、そして重要な対策(検査、駆虫、予防)について詳しく解説します。
主な消化管内寄生虫の種類と注意点
犬猫のお腹の中に寄生する虫には様々な種類がいますが、ここでは特に注意が必要なものをいくつかご紹介します。
1. 回虫(かいちゅう) - Toxocara spp., Toxascaris leonina
- 特徴: 白く細長い、そうめんやスパゲッティのような形状の寄生虫です。成虫は小腸に寄生し、体長は犬で最大18cm、猫で最大10cmほどになります。[回虫の写真またはイラスト]
- 感染経路:
- 母子感染: 母犬・母猫の体内に潜んでいた幼虫が、妊娠中に胎盤を通じて、あるいは出産後に母乳を通じて子へ感染します。子犬・子猫の感染の多くはこの経路です。[1]
- 経口感染: 糞便中に排泄された虫卵(環境中で長期間生存可能)を、他の動物が口から摂取することで感染します。虫卵が付着した土や物を舐めることでも感染します。
- 待機宿主経由: 虫卵を食べたネズミなどを犬や猫が捕食することでも感染します。
- 症状:
- 子犬・子猫: お腹が異常に膨れる(太鼓腹)、下痢、嘔吐(虫体を吐き出すことも)、栄養不良による発育不良、毛ヅヤが悪くなる、咳(幼虫が体内を移行するため)などが見られます。多数寄生の場合、腸閉塞や胆管閉塞などを起こし、命に関わることもあります。
- 成犬・成猫: 感染しても無症状なことが多いですが、免疫力の低下などにより症状が出ることがあります。
- 人への影響(トキソカラ症): 犬回虫・猫回虫は人にも感染します(人獣共通感染症)。 人が虫卵を口にしてしまうと、幼虫が人の体内を移行し、眼(視力障害)、肝臓、肺、脳などに侵入して様々な障害(幼虫移行症)を引き起こす可能性があります。特に、公園の砂場などで遊ぶ小さなお子様は、無意識に汚染された砂を口にしてしまうリスクがあるため注意が必要です。
2. 鉤虫(こうちゅう) - Ancylostoma spp., Uncinaria stenocephala
- 特徴: 体長1~2cm程度の小さな白い虫で、口の部分に歯や板のような構造(鉤)を持ち、これで小腸の壁に噛みついて吸血します。[鉤虫の写真またはイラスト]
- 感染経路:
- 経口感染: 糞便中に排泄され、環境中で発育した幼虫を口から摂取することで感染します。
- 経皮感染: 幼虫が直接皮膚を突き破って体内に侵入します。足の裏などから感染することがあります。
- 母乳感染: 母犬・母猫の母乳を介して子へ感染します。
- 症状: 吸血による貧血が最も大きな問題で、特に体力のない子犬・子猫では重度の貧血により命を落とすことがあります。便が黒っぽくなる(血便、タール便)、下痢、食欲不振、体重減少、削痩(やせること)、毛ヅヤが悪くなるなどの症状も見られます。
- 人への影響: 人の皮膚に幼虫が侵入すると、皮膚の下を移動しながら痒みの強い赤い線状の皮膚炎(皮膚幼虫移行症)を起こすことがあります。
3. 鞭虫(べんちゅう) - Trichuris vulpis (主に犬)
- 特徴: 体の前方が髪の毛のように細く、後方が太い、全長4~7cm程度の鞭(むち)のような形状をした寄生虫で、主に盲腸や結腸に寄生します。[鞭虫の写真またはイラスト]
- 感染経路: 糞便中に排泄された虫卵(環境抵抗性が非常に強く、土壌中で数年間生存可能)の経口摂取。
- 症状: 少数の寄生では無症状なことが多いですが、多数寄生すると、粘液や血液の混じったしつこい下痢(大腸性下痢)、しぶり(便意はあるが出ない)、体重減少、貧血などを引き起こします。重症例では、脱水や電解質異常を起こし、副腎皮質機能低下症(アジソン病)に似た症状(元気消失、食欲不振、嘔吐、虚脱など)を示すこともあります。虫卵の排出が間歇的(常に出るわけではない)なため、糞便検査で見つかりにくいことがあります。
4. 条虫(じょうちゅう) - サナダムシ (Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp. など)
- 特徴: 体がリボンのように平たく、多数の節(片節)が連なった形状の寄生虫です。種類によって長さは様々で、数cmから数mに達するものもいます。[条虫の片節の写真またはイラスト]
- 感染経路: 直接感染することはなく、必ず中間宿主(寄生虫の幼虫が寄生する生物)を介して感染します。
- 瓜実(うりざね)条虫: ノミが中間宿主です。ノミの幼虫が条虫の卵を食べ、そのノミが成虫になって犬や猫に寄生し、犬猫がグルーミングなどでそのノミを口にしてしまうことで感染します。最も一般的な条虫です。([内部リンク -> ノミ・ダニ予防ガイドへ])
- 猫条虫、テニア属条虫など: ネズミやノウサギ、カエルなどを捕食することで感染します。
- マンソン裂頭条虫: カエルやヘビなどを中間宿主(待機宿主)とし、それを食べることで感染します。
- エキノコックス(多包条虫、単包条虫): キツネや犬を終宿主とし、野ネズミを中間宿主とします。人が感染すると重篤な肝機能障害などを引き起こす重要な人獣共通感染症ですが、現在のところ滋賀県での自然界での定着は確認されていません(北海道などで主に問題となっています)。
- 症状: 多くは無症状か軽度ですが、肛門周りの痒み(お尻を地面にこすりつける)、下痢、嘔吐などが見られることがあります。お尻の周りや便の中に、米粒や白ゴマのような動く片節(ちぎれた虫の体の一部)が見つかることで気づかれることが多いです。
- 対策: 中間宿主(特にノミ)の駆除・予防や、狩猟・拾い食いをさせないことが重要です。駆除にはプラジクアンテルという成分を含む駆虫薬(例:ドロンシット®注射液[17])が有効です。
5. 原虫類(コクシジウム、ジアルジアなど)
- 特徴: 上記の蠕虫(ぜんちゅう:いわゆる「虫」)とは異なり、顕微鏡でしか見えない単細胞の寄生虫です。
- 症状: 主に下痢を引き起こします。特に子犬・子猫や、ストレス・免疫力の低下などがある場合に重症化しやすく、脱水や栄養不良を起こすことがあります。
- 対策: 糞便検査(特殊な方法が必要な場合も)で診断し、それぞれに有効な抗原虫薬で治療します。一般的な蠕虫用の駆虫薬は効果がありません。 環境中にオーシスト(抵抗性の高い形態)が排出されるため、同居動物への感染や再感染を防ぐために、環境の清掃・消毒(熱湯や特定の消毒薬)も重要になる場合があります。
【補足】トキソプラズマ症について
- 原因: トキソプラズマという原虫が原因です。猫が主な終宿主ですが、犬や人も含め多くの温血動物が中間宿主となります。
- 感染経路: 猫は主に、トキソプラズマのシストを持つネズミなどを捕食することで感染します。感染した猫は、初めて感染した後の短い期間(通常1~3週間)のみ、糞便中にオーシスト(卵のようなもの)を排泄します。犬や人は、このオーシストで汚染された土壌や水、あるいは加熱不十分な肉(豚肉、羊肉など)に含まれるシストを摂取することで感染します。
- 症状: 健康な犬猫や人では、感染しても無症状か軽い風邪様症状で済むことがほとんどです。しかし、子犬・子猫や免疫力の低下した個体では重症化することがあります。
- 人への重要性: 妊娠中の女性が初めて感染した場合、胎児に影響を与え、先天性トキソプラズマ症(流産、死産、水頭症、視力障害など)を引き起こすリスクがあります。
- 予防:
- 猫: 室内飼育を徹底し、狩りをさせない。生肉を与えない。猫トイレは毎日清掃する(オーシストは排泄後1~5日で感染力を持つため、早期の処理が有効)。
- 人: 肉は十分に加熱調理する。野菜や果物はよく洗う。土いじりの後はよく手を洗う。猫トイレの掃除は毎日行い、妊娠中の女性は可能な限り避けるか、行う場合は使い捨て手袋を着用し、掃除後はよく手を洗う。
- 治療: 症状が出ている場合の治療薬(抗生物質など)はありますが、一般的な駆虫薬は効きません。
診断方法:糞便検査の重要性
お腹の虫の多くは、糞便検査で虫卵や虫体の一部を見つけることで診断します。
- なぜ必要か?: 症状がなくても感染していることがあるため、定期的な検査が重要です。特に子犬・子猫を迎えた時や、下痢などの症状がある時には必須の検査です。
- 検査方法: 新鮮な便を少量採取し、顕微鏡で虫卵などを探します。寄生虫の種類によっては特殊な検査法(浮遊法、沈殿法、直接塗抹法など)や、抗原検査キットを用いることもあります。
- 注意点: 虫卵は常に便に排出されるわけではないため(間歇的排泄)、1回の検査で陰性でも、感染を完全に否定できるわけではありません。 疑わしい場合は、期間をあけて複数回の検査を行ったり、症状や状況から駆虫薬の試験的な投与を行ったりすることもあります。
※年に1~2回の健康診断の際には、糞便検査も合わせて行うことを強くお勧めします。 ([内部リンク -> 健康診断ページへ])
治療と予防
消化管内寄生虫の対策は、「駆虫(治療)」と「予防」の両面から考えることが重要です。
駆虫薬
- 種類: 寄生虫の種類によって有効な薬が異なります。回虫・鉤虫などに広く効く薬、条虫に特異的に効く薬(例:ドロンシット®[17])、鞭虫に効果のある薬などがあります。原虫(コクシジウム、ジアルジア)にはそれぞれ専用の薬が必要です。
- 処方: 必ず動物病院で診察を受け、適切な診断に基づいた駆虫薬を処方してもらいましょう。 市販の駆虫薬もありますが、対象となる寄生虫が限られていたり、用量が不適切だったりする可能性があります。獣医師は、寄生虫の種類、ペットの年齢・体重・健康状態に合わせて最適な薬と用法・用量を選択します。
子犬・子猫の駆虫プログラム [1]
- 母子感染のリスクが非常に高いため、症状がなくても、生後数週齢から複数回の予防的な駆虫を行うことが世界的に推奨されています。
- 具体的なスケジュール(開始時期、投与間隔、回数)は、迎えた環境や月齢によって異なりますので、必ず獣医師にご相談ください。
成犬・成猫の定期駆虫/検査
- 屋外へのアクセスがある、他の動物と接触する機会が多い、狩りをするなどのライフスタイルの場合は、感染リスクが高まります。
- 年に1~2回程度の定期的な糞便検査をお勧めします。
- 検査結果やライフスタイルのリスクに応じて、獣医師が必要と判断した場合に定期的な駆虫薬の投与を検討します。
予防薬の活用
- オールインワンタイプの活用: フィラリア予防薬の中には、回虫や鉤虫など、一部の消化管内寄生虫の駆除も同時に行えるものがあります(例:ネクスガードスペクトラ®[15], レボリューションプラス®[16])。これらの薬を通年投与することで、フィラリア予防と同時に、これらの一般的なお腹の虫に対する定期的な駆虫・予防効果も期待できます。
- 注意点: ただし、これらのオールインワンタイプが全ての消化管内寄生虫(特に条虫や鞭虫、原虫類)に効果があるわけではないため、糞便検査によるチェックや、必要に応じた別途の駆虫薬投与は依然として重要です。
環境衛生と感染対策
- 便の速やかな処理: 排泄された便は、虫卵やオーシストの感染源となるため、すぐに片付けましょう。散歩中の便の持ち帰りも徹底しましょう。
- 手洗い: ペットに触れた後や、便の処理後、食事の前には、石鹸でよく手を洗いましょう。
- 感染経路の遮断:
- ノミ予防: 瓜実条虫の感染を防ぎます。([内部リンク -> ノミ・ダニ予防ガイドへ])
- 拾い食い・狩りの防止: 汚染された土壌や、中間宿主となる可能性のある小動物(ネズミなど)との接触を避けましょう。
- 生肉を与えない: トキソプラズマや他の寄生虫感染のリスクを減らします。
人への感染予防(人獣共通感染症対策)
ペットの消化管内寄生虫の中には、人に感染するものがあります。特に注意が必要なのは**回虫(トキソカラ症)**です。お子様がいるご家庭では特に以下の点にご注意ください。
- ペットの定期的な糞便検査と駆虫: ペットが感染源とならないようにすることが最も重要です。
- 手洗い: 外から帰った後、食事の前、土いじりの後、ペットに触れた後は、石鹸でしっかり手を洗いましょう。お子様にも手洗いの習慣をつけさせましょう。
- 便の適切な処理: ペットの便は速やかに、衛生的に処理しましょう。
- 砂場の管理: 公園などの砂場は、犬や猫の糞で汚染されている可能性があります。遊んだ後は必ず手を洗い、砂場を使用しない時はシートで覆うなどの対策が有効です。
- 生野菜はよく洗う: 土が付着している可能性のある野菜は、流水でよく洗いましょう。
- トキソプラズマ対策: 上記に加え、肉は中心部まで十分に加熱調理すること、猫のトイレは毎日清掃すること(妊娠中の女性は特に注意)が重要です。
まとめ:見えない敵から守るために
お腹の虫は、目に見えなくてもペットの健康を蝕み、時には人の健康にも影響を与えます。特に子犬・子猫や、屋外に出る機会のあるペットは、定期的なチェックと対策が必要です。
定期的な糞便検査と、必要に応じた適切な駆虫、そしてノミやフィラリアなどの外部寄生虫予防(条虫や他の病気の予防にもつながる)を組み合わせることが、効果的な対策となります。月1回の投薬でフィラリアと一部のお腹の虫を同時に予防できるオールインワンタイプの予防薬の活用も有効です。
どの寄生虫に注意が必要か、どのような予防・駆虫スケジュールが良いかは、個々のペットの状況によって異なります。ぜひ一度、当院にご相談ください。
- 寄生虫予防【総合ガイド】へ戻る
- 予防医療(ピラーページ)へ戻る
- ご相談・ご予約はこちら: [ここに電話番号や予約リンクを記載]
参考文献
- [1] 竹内和義(監修). 子犬と子猫の診療ガイド. 緑書房.
- [5] 石田卓夫(総監修) (2020). 犬の内科診療 Part 1. 緑書房.
- [14] ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社. フロントライン® プラス ドッグ 添付文書 (2022年6月改訂).
- [15] ベーリンガーインゲルハイム アニマルヘルス ジャパン株式会社. ネクスガード® スペクトラ 添付文書 (2024年11月改訂).
- [16] ゾエティス・ジャパン株式会社. レボリューション® プラス 添付文書 (2021年10月改訂).
- [17] エランコジャパン株式会社. ドロンシット®注射液 添付文書 (2021年9月改訂).
- (その他、必要に応じて人獣共通感染症に関する公的機関の情報源(CDC、国立感染症研究所など)や、原虫に関する資料を追加)